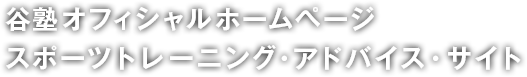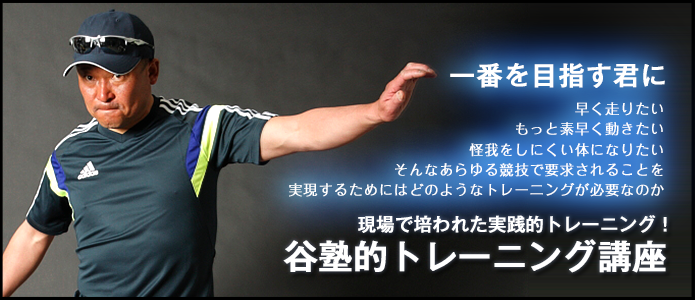
『勝敗を分ける0.1秒の差を生むステップ・ワーク』
【はじめに】
プレーヤーなら誰しも速く動きたいという望みがある反面、それが妨げられている動きを多く目にする。速く動こうとしているが、効率的な動きとの間にはギャップが生じてしまっている。現状の動きと効率的な動きが生むスピードの差を数値化し、その差がサッカーの局面おいてどのような実戦的な違いとして現れてくるのかを、計測結果をもとに提示したい。
【計測の目的】
より速い方向変換をする為には、進行方向により大きな地面反力を得られる接地をすることが必要となる。その接地には三つのキーファクターがある。
1. パワー・ポジションで接地する・・最も大きな地面反力を得られるスタンスでの接地。
2.膝と足首をロックした接地・・膝や足首の屈曲による時間のロスをなくす接地。
左:膝と足首をロックした状態
右:膝と足首がロックされていない状態
3. 全身をパックした接地・・身体を一つの固まりにしてより大きな地面反力を得る接地。
これらの接地の仕方によるスピードの違いを数的に把握し、その差がサッカーの局面においてどのような差を生み出すのかを考察することを本計測の目的とする。
【計測方法】
今回は、膝と足首をロックした場合としなかった場合にフォーカスして2種類のターンを計測した。
1つ目は、前から後ろへのターン(前向き→ターン→バックステップ)、
2つ目は、後ろから前へのターン(バックステップ→ターン→前向き)である。
オーガナイズは、スタート地点と同じくゴール地点になる箇所に、光電管による計測機器を設置し、スタート地点から2m離れたラインを越えてターンして戻る。
ラインを靴一足分以上越えたり、スリップしてターンしたりした場合は再試技とした。
間隔を2mとしたのは、ターンの違いによるタイム差にフォーカスする為である。距離が長いとスプリント能力が数値に反映されてしまい、距離が短いとアジリティ(動→動)というよりクイックネス(静→動)の比重が高くなってしまうと考えたからである。
被験者は、ヴァンフォーレ甲府のアカデミー選手、U-10からU-18までの選手100名で行った。
【計測結果】
計測結果を※表1に示す。
※表1
★前→後ろへのターン
| 被検者数(名) | 速度上昇選手(名) | 変化率(%) | 最大差(秒) | 平均差(秒) | |
| U-10 | 12 | 9 | 75 | 0.23 | 0.09 |
| U-11 | 16 | 10 | 62.5 | 0.18 | 0.09 |
| U-12 | 16 | 8 | 50 | 0.23 | 0.14 |
| U-14 | 18 | 16 | 88.9 | 0.35 | 0.16 |
| U-15 | 14 | 11 | 78.6 | 0.44 | 0.23 |
| U-16 | 6 | 6 | 100 | 0.26 | 0.17 |
| U-17 | 8 | 8 | 100 | 0.28 | 0.12 |
| U-18 | 10 | 9 | 90 | 0.35 | 0.19 |
| 合計/平均 | 100名 | 77% | 77% | 0.29秒 | 0.15秒 |
★後ろ→前へのターン
| 被検者数(名) | 速度上昇選手(名) | 変化率(%) | 最大差(秒) | 平均差(秒) | |
| U-10 | 12 | 11 | 91.7 | 0.41 | 0.2 |
| U-11 | 16 | 12 | 75 | 0.36 | 0.16 |
| U-12 | 16 | 12 | 75 | 0.58 | 0.25 |
| U-14 | 18 | 16 | 88.9 | 0.32 | 0.18 |
| U-15 | 14 | 13 | 92.9 | 0.35 | 0.2 |
| U-16 | 6 | 6 | 100 | 0.29 | 0.15 |
| U-17 | 8 | 6 | 75 | 0.32 | 0.15 |
| U-18 | 10 | 10 | 100 | 0.43 | 0.19 |
| 合計/平均 | 100名 | 86名 | 86% | 0.38秒 | 0.19秒 |
計測結果をまとめると、
前から後ろへのターンでは、
全選手のうち77%の選手が平均0.15秒、
後ろから前へのターンでは、
全選手のうち86%の選手が平均0.19秒、
膝と足首をロックしたターンの方が速かった。
【備考】
ロックしない方が速かった選手は、ロックして接地していても、スタンスが広すぎてパワー・ポジションから大きく外れてしまい、受け取る地面反力が小さくなってしまっているケースと、下半身を捻り込んで接地しても、ロック出来ず屈曲してしまっているケースが観察された。
【考察】
このタイム差は距離にするとどの位の差となるのか?
全選手の10mスプリントの平均スピードは1.98秒。このスピードで動く選手の0.1秒差は、距離にすると50cm。双方のターンの違いによる平均値は0.17秒。これを距離にすると85cmとなる。
つまり、ターンの違いで平均85cmの差が生まれてくるということになる。
85cmは靴約3〜4足分。
では、この差がサッカーの局面において、どのような差となって現れてくるのかを挙げてみる。
・ 今まで抜かれていた相手に身体を入れ込んで、マイボールにすることができるようになる。

・ わずかに届かなかったボールがクリアできるようになる。
・ 今まで届かなかったシュートがブロックできたり、弾くことができたりするようになる。
・ 今まで触れられなかったパスやクロスに合わせることが出来て、シュートに結びつけることが出来るようになる。
・ リーチ出来る距離が伸びる二次的な効果として、予測・ポジショニング・判断に余裕が生まれ、結果的に力みが排除されてエネルギーのロスが防がれ、スピードも上がることになる。
故に、この差は確実に「勝敗を分ける差」であると言える。
【今後の実証的課題】
今回は「膝と足首をロックする」することにフォーカスして速度計測のみを行ったが、ロックした時としなかった時の筋肉のストレスを筋電図で数値化したり、スタンスの違いや全身をパックすることによる地面反力の違いをフォース・プレートで数値化したりすることにより、効率的な動きを更に客観的に数値化することができれば、より説得力のある提示ができると想定される。
具体的には、膝と足首をロックした時とそうでない時では、前から後ろのターンであれば大腿四頭筋が、後ろから前のターンであれば、ハムストリングと下腿三頭筋の筋活動に非効率的な差が生じること。スタンスの違いにより、パワー・ポジョンを外すと推進力と地面を押さえる力に差が生じ、ピッチ上のスピードに変化が生じること、が想定される。これらを数値化して効率的な動きを実証していくことが今後の課題と考えている。
今回は、「関節をロック」することにフォーカスした計測結果であるが、パワー・ポジションで接地すること、全身をパックして接地することにより、更なる効率的なスピードの向上が想定される。
【計測協力】
株式会社 スポレングス
質問、感想はメールフォームからお願いいたします。
なお、質問の回答は質問者のお名前は伏せた形で、まとめてWebサイトへ掲載させていただきます。
(回答まで時間を頂く場合があります)
オススメリンク
▼野球専用トレーニングキット「タニラダー for BASEBALL」
▼ラダートレーニングの決定版『タニラダー』紹介映像
▼タニラダー講習会イメージ
▼切り返しやドリブルが速くなる!タニラダーアドバンスドセット新登場【タニラダー】